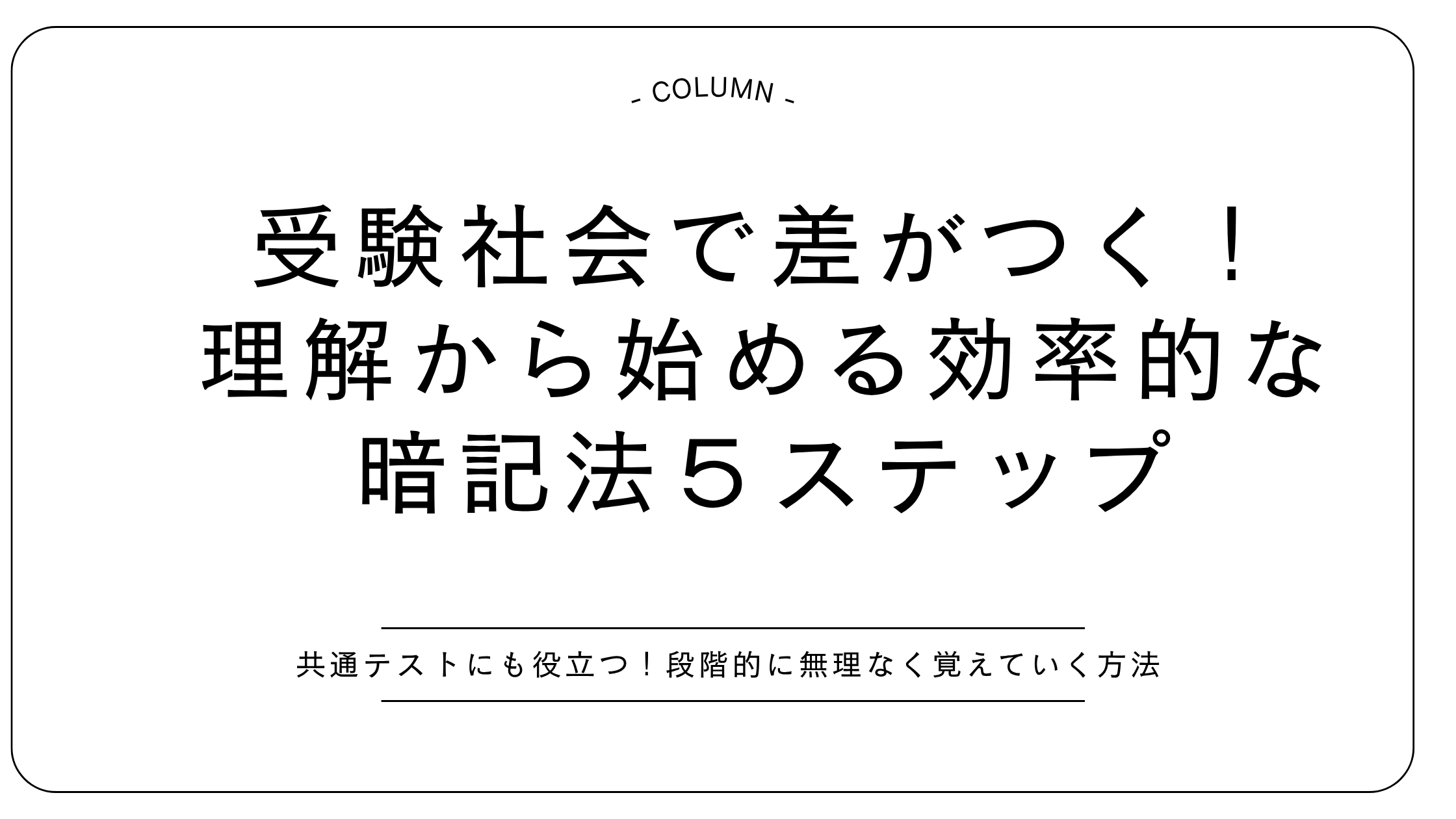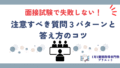「社会が苦手」「覚えるのが苦手」という声をよく耳にします。
どうすれば効率よく、しかも無理なく覚えられるのか。
今回は、私が長年の指導で実践してきた社会の暗記法を段階的にご紹介します。
(1)受験社会で「覚えること」がなぜ大切か
社会は「暗記科目」と言われます。その理由は明快で、覚えていないと解けない問題が多いからです。
実際に多くの入試では、基本的な知識を問う問題が中心です。特に難関私大などでは、細かな知識の再現が要求される傾向にあります。
一方で、大学入試共通テストの登場以降は、思考力・読解力・情報処理力も重視されるようになりました。
しかし、これらの力も「基礎知識」があってこそ発揮できるものです。
つまり、暗記は今後も受験社会において絶対に欠かせない力だといえます。
(2)社会で効率よく覚える5つのステップ
ここからは、私が考える「段階的に覚える勉強法」を5つのポイントで紹介します。
- 暗記よりも内容理解が先立つべき
- 理解とはストーリーと全体像をつかむこと
- 子どもは無意識に「わかったふり」をする
- 暗記教材は空欄補充→一問一答の順で
- 答える形式は選択式→適語補充の順で
① 暗記より内容理解が先立つべき
人は「理解していないこと」を覚えることはできません。
しかし受験指導の現場では、「とにかく暗記を!」という方針をよく見かけます。
これでは一時的に点が取れても、応用がきかず、学年が上がるほど限界が来ます。
まずは内容を理解した上で暗記に入る。これが基本です。
② 内容理解とは「ストーリー」と「全体像」をつかむこと
理解を深めるには、ただ用語を覚えるのではなく、物事の因果関係と単元全体の構造をつかむことが大切です。
- 地理なら「地形・気候と産業の関係」
- 歴史なら「事件とその背景」
- 公民なら「思想と制度のつながり」
こうした「ストーリー」を意識することで、知識がバラバラにならず整理されます。
私はこれを「タンスの棚」にたとえています。知識をどの棚に入れるかを明確にすることで、整理された理解ができます。
③ 子どもは無意識に分かったふりをする
指導の中でよく感じるのが、「わかったつもり」になっているケースです。
例えば、江戸時代の農具改良を学んでいるときに、次のような質問を受けたことがあります。
- 「稲って何ですか?」
- 「脱穀ってどういう意味ですか?」
- 「農具が変わると、なぜ生産量が増えるんですか?」
大人からすれば当たり前のことも、子どもにとっては未知の概念です。
だからこそ、「理解している」と思い込まず、丁寧に確認する姿勢が重要です。
④ 暗記教材は「空欄補充」→「一問一答」へ
社会の暗記教材には主に2種類あります。
- 空欄補充系(文章や図の中で答えを入れる)
- 一問一答系(単語や短文で問う)
多くの生徒は一問一答から始めがちですが、実は順序が逆です。
まずは空欄補充型で、文脈の中にある知識を確認しながら覚えるのが効果的です。
全体像が見える状態で覚えることで、知識の関連性を維持できます。
空欄補充である程度理解が定着したら、一問一答に進みましょう。ここではスピードと反射を鍛える段階です。
⑤ 答える形式は「選択式」→「適語補充」へ
最後に、実際に答える形式のステップです。
いきなり「書いて答える」形式から始めるとハードルが高く、挫折の原因になります。
そこでおすすめなのが、まず選択肢問題を挟むことです。
自分で簡単に選択肢問題を作ることも可能です。
- まず問題を一通り眺める
- 模範解答を参考に、別紙にいくつかの選択肢を作る
- その選択肢を使って解いていく
このように段階を踏めば、知識をストレスなく定着させることができます。
(3)まとめ|理解→整理→暗記の流れを意識して
ここまで、受験社会の「無理なく覚える方法」を紹介しました。
私が特に重視しているのは、以下の2点です。
- 「理解」なしに暗記は成立しない
- すぐ書かせるのではなく、選択式から段階的にステップアップする
この2つを意識して学習すれば、社会の勉強が確実に楽になります。
知識が整理されている生徒ほど、得点も安定します。
ぜひこの方法を試して、社会を得点源に変えていきましょう。
1対1指導塾ブリエットでは、こうした理解中心の学習法を大切にしています。
暗記に苦手意識を持つ生徒も、段階的な学び方で着実に伸びています。
興味のある方はお気軽にお問い合わせください。