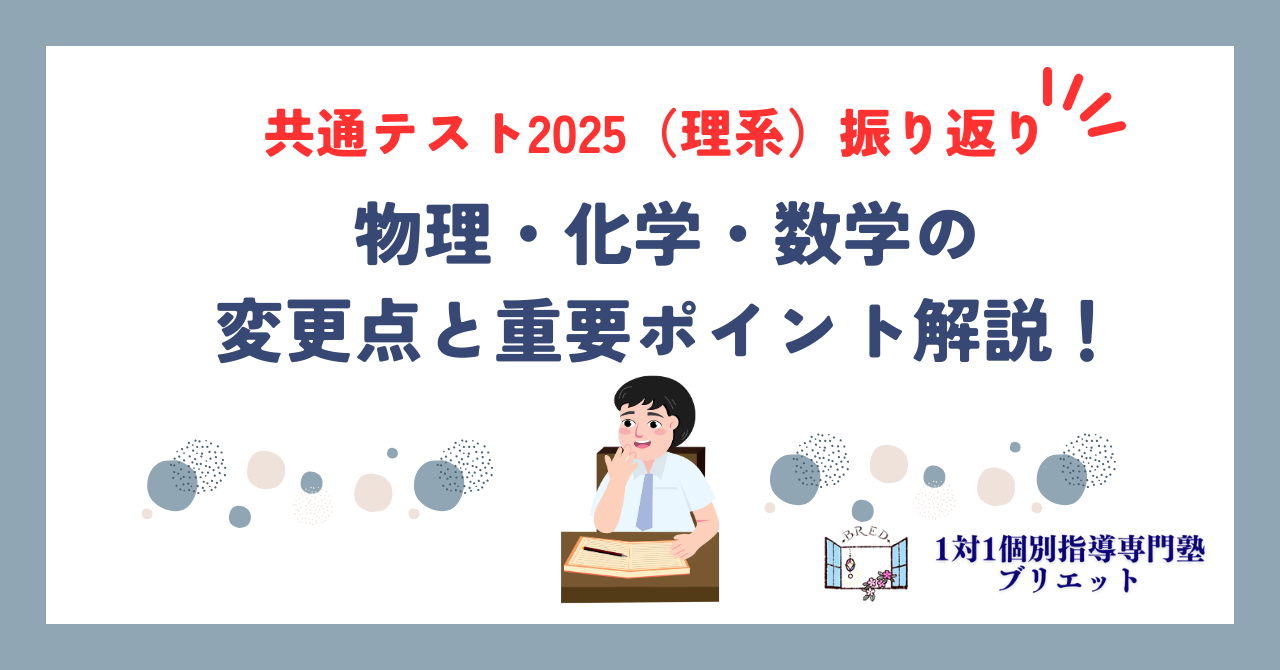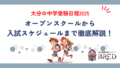共通テストは毎年、出題傾向や問題の難易度に変化が見られます。
2025年の共通テストにおける物理・化学・数学の概要を、わかりやすく解説していきます。
物理の傾向と特徴
2025年度の共通テスト「物理」は、全体の問題数が昨年度の22問から24問へと増加しましたが、大きな変化とは言えない範囲でした。大問数は4題で変わらず、出題形式もほぼ例年通りです。
特筆すべきは、「実験とその考察」に関する問題の難易度がやや上昇した点です。昨年度の問題は、考察に重点を置くものの、数式を活用した論理的な思考力を求める問題は少なく、公式を覚えていれば解けるものが多く見られました。
しかし、今年度は考察だけでなく、立式を必要とする高度な思考力を求める問題が増え、全体的に難易度が上昇した印象です。このような傾向から、物理の対策としては、公式の暗記に頼るのではなく、物理現象の本質を理解し、実験やデータの解析を重視した学習が求められます。
化学の傾向と特徴
化学の問題数は昨年度の31問から34問へとやや増加しましたが、大問数は5つで変わりませんでした。旧課程の選択問題は1問を除き昨年と同じ内容であり、その1問もエンタルピーと熱化学方程式の違いのみで、大きな変更はありませんでした。
ただし、初見の設定を読み取る必要がある問題が増加しました。たとえば、以下のような問題が出題されました。
沸点上昇度を考慮した塩化ナトリウムの析出
NaI(ヨウ化ナトリウム)に関する一連の反応
バナジウム化合物とEDTAに関する反応
これらの問題は、知識と演習経験を活かして新しい問題に対応できるかどうかが得点を左右する内容でした。
今後の対策としては、知識の暗記だけでなく、それをどのように初見の問題に応用するかを考えるトレーニングが重要となります。
数学I・Aの傾向と特徴
2025年度の「数学I・数学A」では、大問数の変更が大きなポイントとなりました。従来は5つの大問があり、3~5の中から2つを選択する方式でしたが、今年は4つの大問がすべて必答となりました。
この変更の背景には、新学習指導要領で「整数の性質」が「数学と人間の活動」に統合されたことがあります。そのため、選択問題がなくなり、受験生の解答の幅が狭まりました。
さらに、新課程で追加された内容がすべて出題されました。
データの分析:「外れ値」と「仮説検定」
場合の数と確率:「期待値」
特に「仮説検定」は、試作問題とほぼ同じ形式で出題され、新学習指導要領を反映した内容となっていました。
問題量と難易度については、文章量とマーク数がやや増加したものの、計算量の少ない問題が含まれていたため、全体の負担は大きく変わらなかったと考えられます。また、一部の問題(図形と計量、空間図形など)は難しかったものの、全体的には例年並みか、やや簡単になった印象でした。
数学II・B・Cの傾向と特徴
「数学II・数学B・数学C」は、2024年までの試験から大幅に変更されました。
以前は5つの大問のうち3~5から2つを選択
今年は7つの大問のうち4~7から3つを選択
制限時間が60分から70分に延長
表面的には問題数が増えたように見えますが、大問1と大問2は、以前の大問1を分割したものなので、内容の総量自体は大きく変わりませんでした。ただし、選択問題の増加によって、試験全体の戦略が問われるようになりました。
新学習指導要領の影響も顕著で、
「平面上の曲線(2次曲線)」が除外され、「複素数平面」のみが出題
「統計的な推測」では仮説検定が出題され、試作問題にはなかった「片側検定」が含まれた
数学I・Aと数学II・B・Cの両方で「仮説検定」が登場し、新学習指導要領の方針が強く反映されていました。
まとめ
2025年度の共通テストでは、
物理:考察と立式のバランスが変化し、難易度が上昇
化学:知識を活用して初見の問題に対応する力が求められる
数学I・A:大問選択制が廃止、新出題内容がすべて登場
数学II・B・C:選択問題の増加と仮説検定の出題
これらの変化を踏まえ、これからの受験対策では、知識の暗記だけでなく、思考力や問題対応力を強化することがますます重要になります。
受験生が柔軟に対応できるよう、普段から幅広い問題に取り組むことが求められます。
保護者の皆様も、お子様がこうした変化に対応できるよう、日々の学習のサポートをお願いいたします。