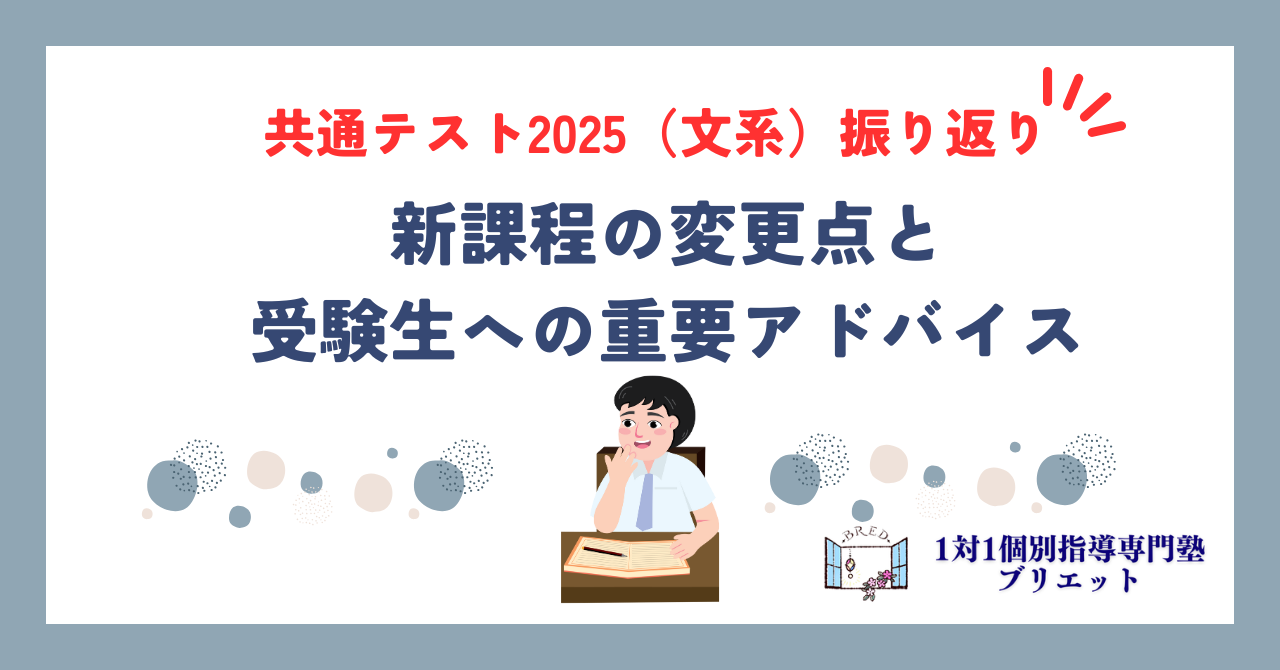2025年1月実施の共通テストが終わりました。
今年の共通テストは新課程1発目の試験であり、変更点も多々ありました。
この記事では、まず事前に予告されていた本年度の共通テストの変更点をまとめ、次に文系の各科目の振り返りと分析をし、その結果から今後の共通テストへの意識や取り組み方を提言します。
高校生はもちろん、小中学生やその親御さんも知っておいて欲しいことをお伝えするので、ぜひ最後までご一読下さい。
1、新課程の変更点
(1)国語の実用的な文章の導入
国語はこれまで評論文・小説・古文・漢文の4つの大問で構成されていましたが、今回の改訂で実用的な文章が新たに追加され、全体で大問が5つになりました。
これに伴い、試験時間も80分から90分に延長されました。
新たに導入される実用的な文章とは、報告書や法令、報道や案内文などの私たちの日常生活にあふれている文章のことで、小説や評論文よりもより身近で生活感のある文章です。
大学入試の中では目新しいですが、実は高校入試や公立中高一貫校の中学入試ではポピュラーな出題なので、受験生は意外と慣れ親しんだ出題形式とも言えます。
(2)地歴公民の「歴史総合」「地理総合」「公共」の導入と入試科目の再編成
地歴公民は科目の新設と入試科目の再編が行われました。
まず科目の新設については、近現代を日本史世界史の垣根を越えて探究的に学ぶ「歴史総合」、地理情報の収集・再整理・発信に重きを置いた「地理総合」、主権者として資質や社会の課題解決をする力の育成を目指す「公共」が新設されました。
共通テストにおいては、「歴史総合・日本史探究」「歴史総合・世界史探究」「地理総合・地理探究」「歴史総合・地理総合・公共」「公共・倫理」「公共・政治経済」の各科目が設定されました。
(3)「情報」の新設
新たに「情報」が導入され、プログラミングの基礎や情報倫理などが問われます。
(4)数学Ⅱが数学ⅡBCに
数学Bのベクトルが数学Cに移行したことにより、数学ⅡB→数学ⅡBCとなりました。また、数学Ⅱには統計の内容が新たに追加されています。
2、各教科の振り返り(英語R、英語L、国語、地歴公民)
ここからは、2025年1月実施の共通テストにおける文系科目の振り返りをします。
(1)英語R、英語L
全体的には例年と大きく変わらずでした。
英語リーディングは大問が6→8と増えましたが、マーク数は5つ減少、試験全体の語数は減少し、5680語でした。
日常生活からアカデミックなものを扱い、出題の仕方も洗練されつつあり、共通テストとして進化している印象です。
英語リスニングは、新しい形式は出たものの試行テスト通りの形式で、大きな変更はありませんでした。
語数も例年並みです。
(2)国語
国語は大きな変更点が2つありました。
まず、実用的な文章の導入と試験時間が80分→90分に変更されました。
実用的な文章は試行テストよりおそらく解きやすかったのではないでしょうか。
また、現代文(評論文、小説)は生徒同士の議論する場面がなくなり、センター試験時代の形式に回帰しました。個人的にはこのシンプルな形が国語力を問うには最適だと思います。
(3)地歴公民
地歴公民は科目構成が再編され大きな変化をしましたが、内容自体に大きな変化はありませんでした。
個人的な見解ですが、地歴公民はセンター試験の時から徐々に知識の確認から活用の方向に進化しており、今回もその延長線上だという印象です。
しかしながら、特に日本史と世界史については言及すべき点が3点あります。
第一に、歴史総合の出題において世界史内容が一部出題されたことです。
これは日本史選択者には精神的にはつらいところだと思いますが、実は正答率的にはそこまでの影響は感じられませんでした。
第二に、各大問の本文がなくなり、生徒の探究活動になった点です。
各大問の本文は良質なものも多かったのですが、直接的に問題に関わらないものもありました。
しかし、探究活動の記録をしっかり追わないと解けない形式に変更され、普段の学校の授業からこういった探究活動をする重要性がますます増したと感じました。
これに関連して第三に、解き終わるのにかなり時間がかかるようになった点です。
センター試験時代は早い人だと20分くらいで解き終えるのも容易だった場合もありましたが、徐々に資料読解が増えていき、今年の共通テストに関してはスピード勝負、時間勝負の面が明らかに目立ってきました。
特に世界史で解き終わるまで時間がかかったと聞きます。
日本史・世界史がスピート勝負、時間勝負になるのは新しい傾向かと考えられます。
3、来年度以降の受験生へのアドバイス
以上のような分析から、文系科目全体で言えるアドバイスは以下の2つです。
・英語、国語だけでなく、社会ですらスピート勝負、時間勝負が鮮明になっているので、日常的な勉強から時間を計り、スピードを意識した勉強をすべき
・日常生活との繋がりがより強調されており、身の回りの現象などと結びつけながら勉強を進める意識をさらに持つ
特に1つ目の解くスピートが大切なことは今後ますます大切になると思います。
そしてそれは、共通テストを控える高校生だけでなく、小中学生にとっても大切です。
大分県の高校入試は共通テストに合わせて問題が変化しており、中学生もしっかり動向をおさえて、スピードを意識した勉強をすべきだと思います。