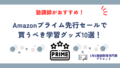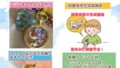はじめに:読書感想文、実はコツさえ知れば簡単です
夏休みの宿題の中でも、毎年多くの生徒・保護者の方から「どう書けばいいのか分からない」と相談されるのが「読書感想文」です。作文や文章を書くのが得意な子でも、「何を書いたらいいのか」「あらすじと感想のバランスが分からない」と戸惑ってしまうこともよくあります。
しかし実際には、読書感想文には“書き方の型”があり、それを知っていればスムーズに、しかも説得力のある文章を書くことができます。さらに、最近ではAI(ChatGPTなど)を活用した読書感想文の書き方にも注目が集まっており、使い方さえ間違えなければとても有効なツールになります。
この記事では、「しっかり書いて評価を狙いたい人」と「とりあえず提出だけ済ませたい人」の2タイプ別に、それぞれに合った読書感想文の書き方を紹介していきます。AIをうまく使うコツや、すぐに使えるテンプレートも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
第1章:本格的に書いて賞や評価を狙いたい人へ
せっかく時間をかけて読書感想文を書くなら、コンクールや学校内での評価も狙いたい。そんなあなたに向けて、本格的な感想文の書き方を、ステップごとに分かりやすく紹介します。
● 本選びから勝負は始まっている
まず大切なのは本の選び方です。「感動した」「驚いた」「自分の考え方が変わった」など、感情が動いた本であることがポイントです。
また、自分の過去の体験や考えと比較がしやすい内容の本を選ぶと、感想文が深みを持ちます。
● 読んだ直後のメモが宝物になる
本を読みながら、または本を読み終えた直後に、心に残った場面や言葉をメモしておきましょう。
大切なのは「何が起きたか」よりも、「なぜ印象に残ったのか」を書くことです。そこにあなたの感情や考えが現れ、それがオリジナリティになります。
● おすすめの構成は「自分との対比型」
読書感想文でありがちな構成は「起承転結」ですが、おすすめは次のような“対比型の構成”です:
- 簡単なあらすじ(100〜150字程度)
- 特に印象に残った場面の説明
- その場面に対して自分がどう思ったか、自分の経験との違いや共通点
- この本を読んで考えがどう変わったか、これからどう行動したいか
この流れを意識するだけで、「感想文らしさ」がグッと上がります。
● よくあるNG例と、その直し方
以下のような書き方は、評価を下げる原因になってしまいます。
- あらすじだけで終わってしまっている → 自分の考えや感じたことを必ず書く
- 「面白かった」「すごいと思った」だけで終わる → なぜそう感じたのか、具体的な理由や体験と結びつける
- 登場人物のセリフをそのまま引用して感想がない → セリフの意味や背景を自分なりに解釈して書く
読書感想文は「読んだ内容」ではなく、「読んでどう感じたか」が最も大切です。評価される文章には、必ず自分の視点があります。
第2章:とりあえず提出したい人向け(短時間で仕上げたい人へ)
「本は読んだけど何を書けばいいかわからない」「とにかく早く終わらせたい」そんな人でも大丈夫。時間がなくても形になる読書感想文の書き方を紹介します。
● 「読んだふり」でも書けるテンプレート構成
以下のような構成に当てはめていくだけで、誰でもそれらしい感想文が書けます。
- 本のタイトルと作者名、ジャンル(例:この本は〇〇さんが書いた、冒険ものの小説です)
- あらすじをざっくり一言で(例:主人公が〇〇をして、最後に△△になります)
- 印象に残った場面(例:私は、主人公が××した場面が心に残りました)
- 自分の考えや経験とのつながり(例:自分だったらどう思うか、どう行動するか)
- 読んで思ったこと・これからやってみたいこと(例:この本を読んで、私も○○してみたいと思いました)
この5ステップを守れば、400〜800字の読書感想文が完成します。
● 使える例文テンプレート
以下のような文を参考に、自分なりに少し変えるだけでもOKです。
この本は〇〇さんが書いた物語で、主人公が△△を通じて成長していく話です。私は特に、主人公が××した場面が印象に残りました。なぜなら、私も似たような経験をしたことがあり、共感したからです。この本を読んで、困難に立ち向かう勇気を持つことの大切さを感じました。私もこれから〇〇な気持ちを大切にしたいと思いました。
まるまる使わずとも、文の順序や言い回しを真似るだけで自然な文章になります。
● 最後のひと工夫で「読んでる風」に見せる
読んだ本に登場するキーワードやセリフを1つだけ入れると、読んだ感がアップします。
また、「主人公は最初〇〇だったけど、だんだん□□に変わったのが印象的だった」など、人物の変化に注目すると、感想らしさが出てきます。
● 書いたあとのチェックポイント
- 「〜と思いました」「〜と感じました」を使っているか
- 文の長さや漢字の使い方がバラバラでないか
- あらすじだけで終わっていないか
これらに注意すれば、提出して恥ずかしくない感想文になります。
● 長い読書感想文(2000字など)を求められたときの対処法
「800字ならすぐに終わるけど、2000字はさすがにキツい…」という声もよく聞きます。特に中学生以上になると、文字数指定が1000〜2000字になることも珍しくありません。
そんなときは、内容を3つ以上の視点に分けて書くのがポイントです。
◆ 書く量を増やすための3つの視点
- ① 本の中で心に残った場面を2〜3つ選ぶ
印象に残った場面が1つだけだと文章量が少なくなります。できれば、「最初に印象に残った場面」「物語の後半で印象に残った場面」のように、複数の場面に分けてそれぞれに感想を書くと、自然と文字数が増えます。 - ② 登場人物の気持ちの変化に注目する
主人公や登場人物がどのように成長したか、考え方がどう変わったかに注目しましょう。そして、「自分だったらどうするか」「その気持ちに共感できるか」を書き加えると、より深い感想になります。 - ③ 自分の経験や考え方と結びつける
読んだ本の内容と自分自身の経験・家族との出来事・学校での体験などを比較してみましょう。「私も似たようなことを経験した」「私は違う考えを持った」というように、自分自身の話を膨らませることで、文章量が自然に増えます。
◆ 全体の構成イメージ(2000字用)
長めの感想文を書くときは、以下のように構成を段落に分けると書きやすくなります:
- はじめに(200〜300字):タイトル、あらすじ、読む前の印象など
- 印象に残った場面①とその理由(400〜500字)
- 印象に残った場面②とその理由(400〜500字)
- 登場人物の変化と自分の考えとの比較(300〜400字)
- 読んで考えたこと・学んだこと・今後にどう活かすか(300〜400字)
段落ごとに小さなテーマを立てて、それぞれにエピソードや自分の意見を加えていくと、「気づいたら2000字」という感覚で書き上げることができます。
◆ 書きやすくなる工夫
- 書く前に「箇条書きメモ」を作ってから書き始める
- 「〜と思った理由」を必ず書く
- 接続詞(たとえば・また・しかし・つまり)を意識して使う
最初から完璧を目指さなくても大丈夫です。まずは書けるところから少しずつ書いていきましょう。
第2.5章:AI(ChatGPTなど)を使った読書感想文の書き方
最近では、ChatGPTなどのAIを使って感想文を書く子も増えてきました。ただし注意してほしいのは、「AIで出てきた文章をそのまま提出する」のはNGということです。
AIはあくまでも“補助ツール”。うまく使えば大きな助けになりますが、そのまま丸写しすると、文章のクセや内容からバレることもあります。
● AIを使うときの基本ルール
- AIが出した文章はそのまま使わず、自分の言葉に直す
- 自分の感情や体験を必ず加える
- 「この本を読んで私はこう感じた」といった自分視点を入れる
先生や読んだ人が知りたいのは、「あなたがその本を読んでどう感じたか」です。AIはそのヒントをくれる存在にすぎません。
● AI活用のおすすめステップ
- あらすじを生成してもらう
「〇〇(本のタイトル)のあらすじを200字で教えてください」と聞けば、簡単なあらすじが出てきます。これを自分なりの言葉で書き直しましょう。 - 感想のヒントをもらう
「この本を読んだ人が考えそうな感想を5つ教えてください」と聞くと、自分に近い視点が見つかります。自分が持った感想を入力して、似たような感想を教えてもらうことも出来ます。 - 文章の構成を提案してもらう
「読書感想文の構成案を作ってください」と頼むと、段落構成のヒントが得られます。それに沿って、自分の言葉で肉付けすれば完成度が上がります。
● AIに頼りすぎないために
AIが出した文章は、読みやすくても「自分らしさ」がありません。例えば、自分の経験や学校での出来事、家族との会話などを絡めて書くと、文章に深みが出てオリジナリティも増します。
また、ChatGPTは無料でも使えますが、使い方によっては似たような文章になりがちです。最初の案を“たたき台”(最初の参考になる文章やアイデアのこと)として、自分の言葉に作り変えるのが一番の使い方です。
● まとめ:AIは便利。でも主役はあなたの言葉
「AI=ズル」ではなく、「AI=参考書」のような存在です。自分で書く時間がないときや、どうしても書き出しが浮かばないときに、ヒントとして活用するのが正しい使い方です。
AIを味方につけながら、自分の体験や気持ちを大切にした感想文を書いてみてくださいね。
第3章:書いたあとにチェックすべき3つのこと
読書感想文を書き終えたら、提出する前にぜひ最終チェックをしましょう。内容がしっかりしていても、ちょっとしたミスで評価が下がってしまうのはもったいないですよね。
① 主語と述語のねじれ、誤字脱字の確認
出来上がった文章を読み返してみると、文の途中で主語が変わっていたり、文の終わりが不自然になっていたりすることがあります。
また、漢字の変換ミスやうっかりした誤字も見落とされがちです。
一度声に出して読んでみると、文の違和感に気づきやすくなります。
② 文体の統一(「です・ます調」に揃える)
感想文では「〜です」「〜ました」という丁寧な文体で統一するのが基本です。
途中で「だ・である」調に変わってしまうと、ちぐはぐな印象になります。全体を読み返しながら、文末の言い回しをそろえましょう。
③ 題名・名前・文字数制限の確認
学校によっては「題名を必ず書く」「800字以内に収める」など、細かい提出ルールが決まっていることがあります。
- タイトルが未記入になっていないか
- 自分の名前・学年があるか
- 文字数が多すぎないか、少なすぎないか
この3点を確認するだけでも、感想文の完成度と信頼感がグッと上がります。
「書いたから終わり」ではなく、「読んでもらう文章」を意識して、最後まで丁寧に仕上げていきましょう。
第4章:ブリエットでは作文や小論文指導も充実!
ブリエットでは、ただ読書感想文の“型”を教えるだけではなく、「自分の考えを自分の言葉で表現する力」を育てる指導を行っています。
● 読書感想文は国語力アップの入り口
感想文の指導を通して、読解力・語彙力・表現力といった、すべての教科に通じる基礎力を養うことができます。
また、「なんとなく感じたこと」を「言葉にして伝える」経験を積むことで、面接や小論文、プレゼンテーションなど、将来にも役立つスキルが自然と身につきます。
● 一人ひとりに合わせた個別添削・アドバイス
生徒によって書く力や課題はさまざまです。ブリエットでは、一人ひとりの書いた文章を丁寧に読み、個別にアドバイスをしています。
「何を書けばいいかわからない」「途中まで書いたけど続かない」といった悩みも、一緒に構成を考えるところからサポートします。
● 絵画を飾った落ち着いた学習空間で集中できる
教室内には美術館のような絵画が飾られた空間があり、静かで集中しやすい環境が整っています。読書や作文にぴったりの落ち着いた雰囲気の中で、じっくりと言葉と向き合うことができます。
● 無料体験授業・個別相談も受付中
「作文が苦手だけど、この夏で少し自信をつけたい」「感想文だけでなく、小論文や面接対策も気になる」など、どんなご相談でもお気軽にお問合せください。
当塾は大分駅から徒歩5分の場所にあり、通塾にも便利です。
夏休み限定の読書感想文講座や作文強化コースも開講していますので、ぜひこの機会にご検討ください。
まとめ:自分に合った方法で、読書感想文をもっとラクに!
読書感想文は、「何を書けばいいのかわからない」と悩みがちな宿題の代表格ですが、書き方の型と目的に合ったスタイルさえ押さえれば、ぐっと書きやすくなります。
今回は、「本格的に評価を狙いたい人向け」「とにかく提出を済ませたい人向け」「AIを活用して効率よく書きたい人向け」と、3つのアプローチをご紹介しました。
どの方法にも共通して大切なのは、自分の考えや感情をきちんと文章にすること。たとえ短くても、自分の言葉で書いた感想文は読む人の心に響きます。
文章を書くのが苦手な人も、夏休みの読書感想文をきっかけに、自分の「伝える力」を育てる第一歩を踏み出してみませんか?
ブリエットでは、文章力を育てる個別指導を通じて、一人ひとりが「書く楽しさ」「伝わる喜び」を実感できるようサポートしています。
作文や感想文でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。